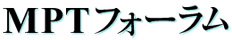■M&A発表日の株価効果に関する要因分析
筑波大学大学院ビジネス科学研究科 加藤英明
[要約]
本研究は,1990年から2002年までの国内上場企業間のM&Aについて,取引の特定の目的や性格が取引全体の経済性に影響を持ち,さらに買収価格の設定が買収企業と買収対象企業間の価値の配分に影響を持つという見通しに基づき,株価効果の要因分析を行っている.分析の結果,救済型M&Aは買収企業,買収対象企業の双方の株主価値増大に貢献していないこと,一方で非救済型M&Aではプラスの株価効果が確認されたが,これは特に水平型取引で顕著であり,プラスの株価効果の要因は事業上のシナジー効果であることが示された.また,買収価格の設定は,買収企業と買収対象企業間の価値の配分を決定付けており,シナジー効果があると考えられる非救済型M&Aでも,高い買収プレミアムの提示は買収企業のプラスの株価効果を消滅させることを発見した.
■株価指数の系列相関と規模別ポートフォリオの相互自己相関*
一橋大学経済研究所 祝迫得夫
[要約]
1960年代末からのTOPIXの収益率の週次データに関して予測可能性を検証したところ,Lo/MacKinlay[1988,1990]のアメリカについての分析結果と異なり,明確な系列相関の存在は発見されず,特に第1次石油危機後のサンプルについてはランダム・ウォーク仮説が棄却できなかった.一方,規模別ポートフォリオのデータを用いて日本の株式市場の自己相関と相互自己相関を分析すると,この点から見た日本のマーケットの構造はアメリカのそれに非常に良く似ている.これらの結果からランダム・ウォークが棄却されない大きな理由は,アメリカの実証で用いられるCRSPの指数に比べ,TOPIXがカヴァーする範囲が大規模銘柄に偏っていることであることが示唆される.実際,日本のデータについて東証2部を含むような単純平均指数を近似的に作成した場合,統計的に有意な強い正の自己相関が存在することが示される.しかし,1990年代後半以降のデータでは規模別ポートフォリオ間の相互関係が崩れており,大型株ポートフォリオの収益率に関して1次の負の自己相関が観察されるようになったことが,その主要な要因の1つであると考えられる.
*本論文の作成にあたって,平成14年度科学研究費(若手研究A14701011),平成14年度特定領域研究「世代間の利害調整に関する研究」からの助成を受けたことを感謝する.竹原均氏には古い期間のデータの入手にあたって御助力いただいた.リサーチ・アシスタントの清水順子氏・中野聖子氏は,分析のためのデータ整備を効率的に行ってくれた.中田勇人氏は本論文の原稿を丹念に読んで問題点・疑問点を指摘してくれた.本誌エディターの浅野幸弘氏とレフェリー,浅子和美,阿部修人,大橋和彦,小幡績,加納悟,岸本一男,高橋一,本多俊毅の各氏,および一橋大学マクロ・金融ワークショップと2002年度ジャフィー冬季大会の参加者,一橋大学国際企業戦略研究科(金融戦略コース)の講義の受講者からは有益なコメントを頂いた.以上の方々すべてに深く感謝する.
■動的因子モデルに基づくグローバル資産市場のリターン予測
─月次リターンの同時確率分布の事前推定─
みずほ信託銀行/筑波大学大学院博士課程 中島英喜
[要約]
本研究は,先進17カ国の株式,債券,通貨市場に関する中島[2002]のリターン・モデルを「確率予測(同時確率分布の事前推定)」の観点から分析し,より有効なモデルと推定方法を検討したものである.分析にあたっては,(1)因子構造に基づく4種類の無相関制約,(2)各因子の動学構造の変更,(3)両者の相乗効果という3つの効果を考え,これらをDawid[1984]のprequential基準によって評価した.この基準は逐次的外挿評価に基づくものであり,一致性と漸近的効率性を有する.また,内挿バイアスを自然に回避できることから,AICのような漸近近似は不要である.さらに,構造変化の検出に優れているため,各モデルの頑健性を評価できる利点もある.検証の結果,上記3つの効果は,適用対象(因子の種類,資産クラス,大規模投機の有無)によって特徴的な差異を示すことが分かった.これは,グローバル資産市場に「因子構造に則した非定常性」が存在することを意味している.なお,こうした非定常性を考慮すると,モデルのリターン予測能力(外挿)は大幅に向上するが,この場合,全ての非定常性を構造化するより,パラメータ制約やサンプリング戦略の変更といったアプローチを併用した方が有効である.
*本稿の作成にあたり,椿広計教授,加藤英明教授,牧本直樹助教授(以上筑波大学)から丁寧な御指導を頂いた.さらに,レフェリーの先生から検証に関する有益な御指摘を頂いた.ここに厚く御礼申し上げたい.なお言うまでもなく,本稿に錯誤があれば著者の責任である.